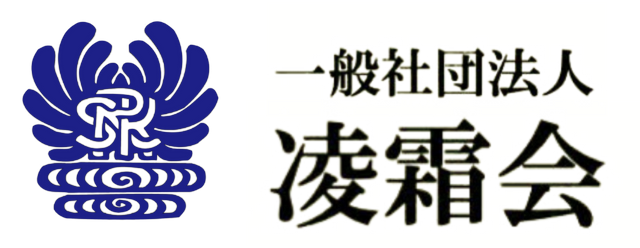凌霜第446号
-1024x726.jpg)
表紙絵 昭37営 有 田 幸一郎
カット 昭34経 松 村 琭 郎
神戸大学凌霜会理事長就任にあたって 小 堀 秀 毅
凌霜会理事長退任のご挨拶 大 坪 清
目 次
◆母校通信 松 尾 貴 巳
◆六甲台だより 行澤一人、鈴木 純、清水泰洋、村上善道
◆本部事務局だより 一般社団法人凌霜会事務局
3月通常理事会/5月通常理事会/ご芳志寄附者ご芳名
事務局への寄附者ご芳名
◆(公財)神戸大学六甲台後援会だより(81)
◆学園の窓
国際協力への思い 内 田 雄一郎
研究者を志した頃のあれこれ 永 合 位 行
対話型ビジネス価値共創人材養成プログラムについて 鈴 木 竜 太
「際」 平 野 実 晴
◆神戸大学の歴史的建造物
その周辺の歴史遺産 小 代 薫
◆表紙のことば ハイデルベルグ(ドイツ) 有 田 幸一郎
戦後の卒業アルバムと学内メディアで見る「ここが変わった神戸大学」 住 田 功 一
◆六甲アルムナイ・エッセー
旧山邑邸建造100年の話 山 邑 陽 一
がら空きの特急電車 若 狭 一 弘
本道からそれた景色も、案外悪くない 多 田 晋 作
◆凌霜ネットワーク
神戸大学体育会アメリカンフットボール部RAVENS創部50周年記念式典・祝宴 三 宅 俊 宏
六甲男声合唱団からのお知らせ 永 井 哲 郎
◆六甲台就職相談センターNOW
新・学問のすすめ 浅 田 恭 正
本と凌霜人「国立大学教授のお仕事―とある部局長のホンネ」 木 村 幹
◆凌霜ひろば
2025万博へ行ってきました 當 麻 芳 輝
◆クラス会 しんざん会、さんさん会、イレブン会、
むしの会、双六会、神戸六七会、与禄会、
昭和43年入学20回生
◆支部通信 東京、三重県、神戸、島根県、広島
◆つどい 神漕会(漕艇部)、水霜談話会、大阪凌霜短歌会、
東京凌霜俳句会、大阪凌霜俳句会、凌霜川柳クラブ、
神戸大学ニュースネット委員会OB会
◆ゴルフ会 名古屋凌霜ゴルフ会、廣野如水凌霜KUC会、
茨木凌霜会、西宮高原ゴルフ倶楽部KUC、
芦屋凌霜KUC会、花屋敷KUC会
◆物故会員
◆国内支部連絡先
◆編集後記 行 澤 一 人
◆投稿規定
神戸大学凌霜会理事長就任にあたって
小 堀 秀 毅(昭53営)
(旭化成株式会社取締役会長)
(日本経済団体連合会副会長)
この度、多くの諸先輩がいらっしゃる中、凌霜会第12代理事長を拝命いたしました。
私は、1978年に神戸大学を卒業して以来、今日まで約半世紀近く産業界に身を置き活動してきました。この間、本学の教育、研究、文化振興に関わる機会や凌霜会会員の皆さまと幅広く親睦を図る機会にはなかなか恵まれませんでしたが、数年前から経済団体の活動に参画し、自社や関連する業界にとどまらず、日本の社会や産業界全般の未来を考える機会を得ました。そうしたご縁もあり、関係者の皆さまにお声がけいただき、昨年6月に凌霜会の理事に就任することになりました。
今回は、理事として活動経験も少ない中、大坪前理事長からのご推挙を賜り、理事長を拝命することとなりました。就任にあたり、東京在住で業務活動も東京中心の私が、凌霜会の理事長としてその伝統を守りつつ、次世代の皆さまにその活動をより一層活性化させ引き継いでいけるのか正直なところ逡巡もいたしました。しかし、現在同活動を支えてくださっている皆さまからの力強いご支援のお申し出が何よりの励みとなり、お引き受けする決意を固めた次第です。
凌霜会は、大正13年に社団法人として設立され、昨年には創立100周年の節目を迎えました。発足以来、歴代の先輩方の力を結集した積極的な活動の連鎖が、長きにわたる歴史と輝かしい伝統を築き上げ、神戸大学出身者のネットワークの要として同窓生と大学、同窓生相互の絆のよりどころとして大きな役割を担ってきております。就任にあたり、皆さまのお力添えを賜りながら、大坪前理事長が取り組まれた活動、成果をしっかりと引き継ぐとともに、時代の変化や新たな価値観にも柔軟に対応し、より創造的で魅力ある活動にも積極的に取り組んでまいりたいと存じます。会員各位にとって有益かつ有意義な組織であり続けられるよう全力を尽くす所存です。
今、世界は、先行きが不透明で不確実な混沌とした時代を迎えています。これまでの「秩序ある国際社会」をベースとした「自由貿易によるグローバル化の進展」という共通の価値観が揺らぎ始めています。第二次世界大戦から、今年で80年を迎えるにあたり、これまで戦勝国である米国の圧倒的な経済力や指導力が、国際社会をけん引してきました。しかし、昨今の米国では、白人を中心とする中間層の没落とそれに伴う格差の拡大が、社会の分断と政治の不安定化を招いています。一方、同じ時期に中国は急速な経済成長と軍事力の拡大により、国際社会に対する影響力を高め、米国は中国との分断・対立を鮮明にし始めました。さらにロシアのウクライナ侵攻により、エネルギーをはじめとした資源確保等の地政学的リスクが高まり、世界主要各国の政治に大きな影響を与えました。結果として、反グローバル化、保護主義が台頭し、政治と経済の密接度が一段と高まり、世界は多極化の様相を強めつつあるように見受けられます。
日本は、戦後米国の背中を追い続けた結果「Japan as No.1」と言われるまでに復興、成長を遂げましたが、その後のバブル崩壊で、今日「失われた30年間」と言われるように、国際社会においてその存在感が低下しています。さらに近年は人口減少に加え、少子高齢化の加速により、深刻な労働力不足が懸念されています。また、デジタルテクノロジーの進化とともにSNSの普及が急激に進み、情報が瞬時に拡散される時代となった今、物事の真偽を判断する必要性に加え、本質を見極める重要性が問われています。価値観の多様化が顕在化し、人工知能(AI)の活用が進む中で、人間の在り方や役割についての倫理観等が改めて問われる時代を迎えようとしています。
このような世の中において極めて重要なことは、将来の目指す姿を描き、中長期視点を持ちながらその実現に向けて軸足を定めたうえで、目先の課題解決に取り組むことであると思います。島国で資源に恵まれない日本においては、カーボンニュートラルな循環型社会、健康で安全・安心な長寿社会の実現、つまり持続可能な社会の実現に向けて、イノベーションを起こし、新たな価値を創出することで、国際競争力を高めて発展、繁栄していくことではないでしょうか。そのためには、国を挙げて産学官一体の取り組み強化、持続可能な社会に貢献するマーケット創出に向けての機運醸成や必要なルール形成で世界をリード、けん引していくことが必要だと思います。
歴史を振り返れば、日本は、明治維新による文明開化や第2次世界大戦敗戦からの力強い復興、成長を遂げ国際社会に仲間入りし、大きな貢献を成し遂げてきました。その重要な源泉の1つが、人材であり、それらを生み出してきた日本の教育や風土にあると思います。
日本人には元来より、勤勉であること、規律を重んじる姿勢、高い倫理観、さらには「もったいない」に象徴される相手を思いやり、物事を大切に取り扱う精神が育まれています。大学には、これら日本人の特長を生かしながら、より多くの海外留学生を受け入れることで多様性の大切さを実感できる環境を育むことが求められています。また、海外に留学する学生を多く輩出すること、チャレンジ精神の土壌をつくり出すリベラルアーツ教育の充実を図ることも重要な使命の一つです。さらに社会に出てからも個性に応じて専門性を磨き上げることのできるよう、学問の基礎やその土台作りに専念できる環境を整備、提供することが、重要な役割として求められるのではないでしょうか。
神戸は港町として発展してきた歴史があり、多様な人・もの・ことを受け入れて共生する精神が根付く日本の中でも極めて国際的な独自の文化を持った地域です。その神戸を地元とするわが母校、神戸大学は、「学理と実際の調和」という建学の理念のもと、「真摯・自由・協同」の精神を発揮し、社会で活躍する多くの人間性豊かな人材を創出してきています。そして現在大学では、藤澤学長のリーダーシップのもと、KU VISION 2030「知と人を創る異分野共創研究教育グローバル拠点」を掲げ、教育研究の活性化・経営安定化に取り組んでいます。その活動は、まさに時代の要請でもある、独創性あるグローバル教育の充実を通してのグローバル卓越人材育成、有機的な異分野共創研究基盤の強化を通じての社会実装、そしてイノベーション創出で将来の目指すべき社会の実現への貢献や社会課題の解決等への取り組みです。
また、1995年1月には、阪神・淡路大震災を経験した地元大学として防災・減災や復興にかかわる研究に取り組み、成果の発信や地域社会への貢献も進めてきており、NPO・市民活動が盛んです。まさに自然災害の激甚化の時代にその経験や教訓を次世代に伝えていく重要な役割も担っています。
凌霜会においても、神戸大学執行部の皆さまの活動を理解し連携をより深めることで、「日本の未来を担う」人材の育成や持続可能な社会実現に向けての研究教育成果の発現等の役割、機能の充実に寄与し、母校の存在感を高めていくことでお力添えできればと願っております。
そのためには、凌霜会自体の会員数を増強し、活動の活性化を図っていくことが重要です。特に現在の会員においては、高齢会員の占める割合が高い状況から、若い世代の卒業生の会員化による増強が喫緊の課題です。人生100年時代といわれる今日、また、先々不透明、不確実な時代だからこそ、世代を超えた凌霜会員が「CONNECT」した活動が重要だと思います。
かつて「終身雇用」が1つのキーワードとして成り立ってきた社会の価値観や制度の中で、活動、活躍してきた会員の皆さまの経験・知見。そして個々人の「終身成長」をベースとした新しい価値観や制度を作り上げていくことで持続可能な社会の実現を担う若い世代の会員の皆さまの挑戦と創造。これらを融合、連携していくことで、新たな気づき、行動が生まれます。そして、それらの活動が、会員自らの成長と神戸大学の知名度向上、および持続可能な社会の実現に寄与していくことになるのではないでしょうか。
凌霜会として、大学の現状や課題、目指すべき姿に必要なビジネス的、経営的視点等を発信することや会員間の活動の活性化に取り組むことで、より母校への関心を高め、母校愛を呼び起こしていきたいと思います。人生で大切にしたい「交わる」「楽しむ」「役立つ」の精神で同窓会運営に臨んでいきたいと思います。
今後とも格別のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
凌霜会理事長退任のご挨拶
大 坪 清(昭37経)
(レンゴー㈱代表取締役会長兼CEO)
退任にあたり一言お礼のご挨拶を申しあげます。
2016年6月に高﨑正弘様の後任として、第11代の凌霜会理事長を拝命いたしました。社業の傍ら、関西経済連合会副会長、関西生産性本部会長の任にも就いているなかでお引き受けすることとなりましたが、よき諸先輩方、代議員、理事、監事、事務局の皆様のご協力を得て何とか全うすることができたのではないかと考えております。
理事長に就任して以降の9年間にはさまざまな出来事、変化がありました。特に2019年に発生した新型コロナウイルス感染症は、世界中で猛威を振るい、我々の生活に大きな影響をもたらしました。人々の移動が制限され、国境を越えての移動はもちろんのこと、都市によっては外出禁止令が出されるまでに至りました。日本国内においても、経済活動が停滞し、業種や業態によっては経済的に非常に困窮した状況に陥りました。政府は、合計3度にわたり緊急事態宣言を発出し、移動を伴う行動の自粛をはじめとする感染防止策を呼びかけたことにより、国民の従来の生活パターンは抜本的な変化を余儀なくされました。
神戸大学においてもその影響は大きく、令和元年度学位記授与式、令和2年度入学式をはじめとした行事が軒並み中止となりました。凌霜会としても、新入生向けの行事を開催することができず、学生との交流の場を失うという事態となりました。ホームカミングデイなどのイベントをすべて中止せざるを得ない状況となりました。
学生時代を振り返りますと、クラブ活動に没頭し、先生方や友人と大いに語り合い、交流を深めるとともに学ぶことも多かったことを懐かしく思い出します。コロナ禍において、そのような経験の場が大きく制限されてしまったことは非常に残念に思います。
その一方で、対面以外でも活動ができる手段としてリモートワークに代表される「新しい生活様式」が普及していきました。今では、皆様も出社することなくさまざまな場所でリモートワークを行ったり、オンラインで会議を開催したりということが日常的なものになっていると思います。コロナ禍を契機として、DXの進展が加速したことも事実です。特にここ数年におけるAI技術の進展は目覚ましいものがあります。
IT技術の進展は、私たちの生活に大きな恩恵をもたらし、パソコンやスマートフォンを使えば、指先ひとつで世界中のあらゆる情報を得ることが可能となっています。そのこと自体は素晴らしいことですが、人々がそれで物事を理解したような錯覚に陥り、自分で考えなくなってしまうことを危惧しています。
私は、まずは自分の頭で考える癖をつけることが最も大切であると考えています。どんなに技術が進もうとも、それを使いこなすのは人間の頭脳に他なりません。自分自身の頭で考え、自分なりの答えを導き出すことが重要なのです。そして、議論を交わし、他人の考えも聞きながら自分なりの答えを見つけていく、その繰り返しによって真の考える力がついていく、すなわち単に賢いだけではなく、「強い頭」となっていくのです。
このような時代であるからこそ、大学を中心とした高等教育において、自分で考える力を高めていく重要性はより一層高まっていると考えます。「学理と実際の調和」を理念とする神戸大学の存在意義も、非常に大きいといえるでしょう。
年号は平成から令和に変わりました。社会も大きな変化を続けており、人口増加と高度成長を前提とした仕組みやデフレ社会に最適化した政策のうえに成り立っていた「昭和モデル」「平成モデル」から脱却し、「令和モデル」といえる『共助経済社会』の実現に向けた取組みを早急に推し進めていくことが必要になりました。DEI、すなわちDiversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包摂性)を尊重し、他者に対するEmpathy(共感)とsympathy(惻隠の情)の心をもって、多様な意見を取り入れ議論を交わしていこうとする姿勢が求められるようになっていると考えています。
「凌霜」は、菊をたたえた漢籍にある言葉であり、神戸高等商業学校初代校長水島銕也先生が命名されました。六甲台学舎本館の玄関前庭に、水島先生の揮毫による「凌霜雪而香」と記された記念碑があります。「人生の試練に耐えて菊のように香り高く美しかれ」という思いが込められています。「VUCAの時代」ともいえる今こそ、改めてこの言葉を胸に刻む必要があるのではないでしょうか。
神戸高等商業学校を発祥とし、社会科学系学部を中心に社会科学の殿堂として大きな地歩を占めてきた神戸大学は、2023年に創立120周年を迎えました。また、凌霜会は1924年9月に社団法人として設立され、昨年2024年に100周年を迎えることができました。凌霜会100年の足跡は、母校神戸大学と共に紡いできたと言えます。凌霜会は私が理事長に就任して以降も多くの取組みを進めてまいりました。2019年からは全国30支部の支部代表者会議を開催しています。奈良支部、播磨支部、東北支部等もあらたに設立されました。凌霜会最大の財産である会員のデータを有効かつ有益に管理活用するために、会員システムの再構築もいたしました。そのほか、会員へのサービス強化に努めてまいりました。
凌霜会の課題は「会員の増強」と「盤石な財政体質の確立」です。それを成し遂げるためにもネットワークの強化が必須です。職域を中心とした縦のネットワーク、同期会を中心とした横のネットワーク、異業種交流を中心とした斜めのネットワークです。それを連綿と後輩に引き継ぎ、凌霜会の絆を強固にすることが必要です。会員には、法曹界、会計士界、実業界など各方面で活躍されている方々が沢山おられますが、高齢化による沈滞傾向があることも事実ですので、特に若い会員の皆様には神戸大学・凌霜会を、日本を代表する組織にするために協力していただきたいと思います。
新たに理事長に就任される小堀秀毅さんは、大企業の経営トップとしてリーダーシップを発揮してこられ、また、日本経済団体連合会の要職を務めてこられていますので、今後の凌霜会を支える柱として、安心してバトンタッチをすることができる方であると考えております。
最後に、今までご支援いただきました皆様に心よりお礼を申し上げ、母校の発展と皆様のご健勝を祈念して退任のご挨拶とさせていただきます。長い間ありがとうございました。