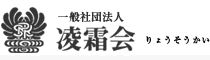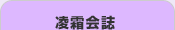凌霜第380号 2009年02月01日

◆巻頭エッセー
裁判員制度はうまくいくのか 馬 場 健 一
◆母校通信 中 野 常 男
◆六甲台だより 吉 井 昌 彦
◆理事長からのメッセージ
六甲台講堂修復について 高 崎 正 弘
◆第3回ホームカミングデイと神戸大学の未来 齊 藤 彰
◆学園の窓
国際協力研究科の取り組み 五十嵐 正 博
私の研究:経済間の所得格差と技術進歩 春 山 鉄 源
法の裁きではなく良心の裁き?
-ロシア文学と陪審裁判― 渋 谷 謙次郎
行き当たりばったりの凡庸な人間 松 島 法 明
◆リレー・随想ひろば
二人のマーフィー「成功の法則」と
「失敗の法則」 立 花 正 昭
企業寿命30年説と100年長寿企業 柳 下 健 二
脱サラ税理士の独り言 大 谷 明
ロンドン語学留学記 木 村 正 則
修習前の一人旅 齋 藤 勝
◆私の大学生活、ISA 田 中 敦 子
◆本と凌霜人
「タートル流投資の魔術」 中 谷 孝 夫
「広田弘毅『悲劇の宰相』の実像」 中 矢 忠 男
「株とギャンブルはどう違うのか・・・
資産価値の経済学」 柴 谷 元
凌霜俳壇 凌霜歌壇
<本号掲載記事から一部抜粋>
◆巻頭エッセー
裁判員制度はうまくいくのか
法学研究科教授 馬 場 健 一
一般市民が刑事裁判に参加する裁判員制度の発足が間近に迫っている。昨年11月末には、全国の有権者から選ばれた約295、000人に2009年の裁判員候補者の通知が発送された。全国平均で有権者352人に1人の確率とのことだから、本エッセーをお読みの方の中にもご自身あるいは周りに候補者に選ばれた方がおられるかもしれない。
もちろん候補者に必ず裁判員の職務が回ってくるわけではない。裁判員裁判に付される刑事重罪事件は年間で3、000件程度と見積もられており、1件あたりの裁判員の数は6名が原則だから、補充要員を含めても実際に選ばれるのは2万数千人といったところであろう。とはいえ実際の選考にあたっては、その何倍もの候補者が裁判所に呼び出されることになるので、ある年に裁判員候補者に選任されれば、正当な辞退理由がない限り、現状ではかなり高い確率で裁判所に呼ばれ、全体の1割程度は裁判員に選ばれると考えられる。裁判当事者でもない一般市民が義務としてこれだけ大量に各地の裁判所に呼び出され、また裁判官と全く同等の職務を負うことは、やはり大変なことである。
裁判員制度の概要や導入の経緯、制度の趣旨や目的、裁判員の権限や義務、また辞退が認められる場合などについては、ここのところ頻繁にメディアで紹介されているところでもあり、ここでは、裁判員制度についてよく語られる問題点のうち、特に裁判員が一般市民であることに関する論点から2~3拾い、簡単ながら考えてみたい。
まず第一にこの制度は、国民にあまり評判がよいとは言えない。各種アンケートではいずれも、「気が進まない」と言った回答が多い。例えば2006年12月の内閣府の調査によると、「参加したい」、「参加してもよい」が計20・8%に対して、「あまり参加したくないが、義務であるなら参加せざるをえない」44・5%、「義務であっても参加したくない」33・6%といった具合である。直近の昨年11月のNHK調査でもほぼ同様で、「ぜひ参加したい」と「参加してもよい」が計33%、「できれば参加したくない」が44%、「絶対に参加したくない」が21%で、若干参加意欲が高まっているようにも思われるが、なお3人に2人までが消極的である。
しかし新しい義務、それも重大な刑事事件に判決を出すという重い義務を課そうというのだから、これまで司法などには無縁であった一般人が忌避したいと感じるのは当然といえば当然である。むしろ、にもかかわらずかなりの国民が、「参加したい」とか「義務ならやむを得ない」と答えている方が驚きであるとも言える。また参加したくない理由も、NHK調査によれば、「仕事や家事などで忙しい」といった私事を優先する理由は11%にとどまり、むしろ多いのは「正しい判断ができるか自信がない」(55%)とか「人を裁く責任を負担に感じる」(26%)といった制度に対する不安の方がずっと大きい。つまり国民の多くは、この新しい公的責務に対して「余計なこと」と反発し、はねつけているのではなく、「そんな重大なことに自分などが関わって大丈夫だろうか」と感じているのである。謙虚で真面目な日本人的反応といったところであり、最近の日本人は私生活優先で公共心が失われているなどという人口に膾炙したイメージへの反証例ともいえる。NHKの調査ではまた、参加したい人の割合は若い人ほど高い(20代54%、60代28%など)というのも興味深い。
このような調査から引き出される結論は従って、「不評だから中止」などというものではなく、「参加者の不安と負担をできる限り解消する努力を払いつつ、導入を進めるべき」と言うものであろう。このような真摯で謙虚な一般市民の参加こそ、裁判員制度で求められているものだと言っても過言ではないからである。
ちなみに当初は気乗りのしなかった一般市民の気持ちが、実際に裁判への参加を果たした後は大きな充実感に変わるというのは、すでに長い市民参加の経験を持つ欧米において往々に見られる反応である。また同じことは日本でも、検察官が起訴しなかった事件について起訴すべきかどうかを一般市民が論じる検察審査会の委員たちについても言える(なお、この検察審査会制度は戦後すでに長いこと運用されてきており、司法への市民参加制度として定着をみている)。ちなみに筆者も講義の一環として学生に裁判傍聴を義務づけ、レポートを提出させているが、最初は負担に感じるのか気乗りしない様子であった者が、実際に裁判所を訪れ傍聴席に座ると、法廷の厳粛な雰囲気とそこで展開されるドラマに強い感銘を受けてくることが多い。講義の感想として、「法廷傍聴の経験が一番よかった」などと書かれて複雑な気持ちになることもしばしばである。
しかし、この「不安と負担」については、制度理解の不足による根拠のないものもある一方で、制度の性格上完全には払拭しきれないものであることも率直に認めなければならない。残酷な犯罪事実について知り、被害者や遺族の悲嘆に身近に接し、被告人の有罪無罪を決定し、死刑も含めた重い刑罰を科さねばならないというのは、やはり大変なことである。特に死刑判決を出すことは、職業裁判官にとってさえ一般に大変辛い経験であり、ましてやいきなり裁判員に選ばれた者にとっての心理的負担は想像するに余りある。この点については十分なケアを考える必要があるが、民主主義体制の中、主権者国民によって死刑制度が支持されている以上、こうした重大な決定とそれに伴う苦悩は、職業裁判官だけでなく、国民代表ともいうべき立場である裁判員も共有し、その苦悩をさらに一般国民が受け止めながら、死刑制度(さらに広くは犯罪と刑罰一般)についての理解と議論を深めるよすがとすべきものであろう(なお付言しておくと、殺人事件などにおいても、裁判官が遺体の写真を実際に見ることは、その是非はともかく、あまりないとのこと)。
職業裁判官とともに結論を出す裁判員制度においては、誤った判断が増える、という批判はあまり聞かないが、他方でよく言われるのが、素人の裁判員は裁判官に判断を一任しがちなのではないかとか、専門家である裁判官とは対等に議論できないのではないか、といった点である。先に触れたとおり、裁判員は「正しい判断ができるか自信がない」といった心理状態にあり、また日本人は権威すなわち「お上」に弱いなどとも言われる。また自分の意見をうまく言葉で伝えたり、他人と冷静に議論する経験が少なく、論理性や合理性が生命である裁判実務には適さない、という批判である。
日本には戦前においてさえ陪審裁判を行った経験があり、当時の陪審員は適正に職務を果たしたと伝えられている。また、先に触れた検察審査会制度が定着していることからしても、そのような批判は正当なものとは思われない。多くの日本人は非論理的・非合理的であって、きちんと考えること、話をすることもできないなどと果たして言えるであろうか。むしろ日本人は一般に教育水準も高く、まっとうに思考し判断する能力もあると言うべきであって、要はどうしたらそうした資質を引き出していけるかをこそ、制度の側が考えるべきであろう。この点でむしろ危惧されるのは、裁判員制度を内心では歓迎していない、あるいは一般市民を見下したエリート意識の染みついた裁判官が、裁判員に対して権威的に臨むなどして自分が適切だと考える結論を押しつけるような事態であろう。
最後に、裁判員には守秘義務が課せられているから、こうした問題裁判官に当たったような経験さえも一切話せないといった誤解があるが、制度の問題点を一般的に論じることは禁じられていないどころか、裁判員制度を適正に運用するために望ましいことでさえある。また守秘義務と言っても誰しも自分の職業や日常生活を通じて、人のプライバシーや安全、利益を守るためなど公言できない情報に接することは、実は通常のこととも言える。
筆者としては、現行刑事司法の改革のために導入された裁判員制度である以上、「うまくいくのか」ではなく、むしろ「どうしたらうまくいくのか」を考えたいと思う。
◆理事長からのメッセージ
六甲台講堂修復について
社団法人凌霜会理事長 高 正 弘
「東(ひむがし)の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月かたぶきぬ」
学生時代に誰もが一度は口ずさんだ柿本人麻呂の一首で、幼い日の軽皇子(後の文武天皇)の狩のお供をして阿騎野(現在の奈良県宇陀市)に出向いたときに詠んだものと言われています。
これを画題とした作品が、六甲台講堂や図書館に多くの大作を残された洋画家・中山正實画伯(1919年・大正8年高商卒)の「阿騎野の朝」で、現在、宇陀市教育委員会所蔵として同市中央公民館に掲げられ一般に公開されています。
万葉集研究者の間では「画の中央の白馬にまたがる人は誰か。軽皇子はまだ10歳の少年だったし、作者・柿本人麻呂は官位からいって白馬に騎乗できるはずがない」と言った声もあるようですが、昨年5月、同窓「三四会」のメンバー有志と旧大宇陀町を訪ねて大先輩の絵を目にした時の理屈抜きの感動は、後輩の私には忘れられません。舞台となった「かぎろひの丘」に立ち、長歌と4首の短歌からなるこの一連の歌を読めば、1300年余の時空を超える思いがしました。同窓諸兄姉も、早春の一日を「かぎろひ浪漫」に身を委ねられては如何でしょうか。
さて、現在、母校神戸大学に於いては、基金記念事業として六甲台講堂の修復と、これに合わせて、中山画伯の壁画の修復が予定されています。六甲台講堂については既に多くの機会にその歴史が記されており、よくご存知のこと思いますが、以下、第189回「神戸大学百年史編集だより」からその概要を改めてご紹介させていただくと、「神戸大学には現在、国の登録文化財が4つある。いずれも前身校の一つである旧制神戸商業大学の建物として1930年代前半に設置された。その中の一つである講堂は、昭和10年3月に竣工した中世ロマネスク様式の鉄筋コンクリート造りで、建築面積750㎡、正面玄関には背の高い5連アーチが並び、国際貿易都市神戸にふさわしく扉には船の操舵輪を模した装飾が施されている。最上部の丸窓は船の舷窓を連想させ、大海原を渡り世界中で活躍する国際的商業人の育成に努めた旧制神戸高等商業学校水島初代校長の理念が息づくかのようである。建物内部には中山画伯による大壁画3部作「光明」、「富士」、「雄図」がステージを囲んでいる。新制神戸大学でも入学式や卒業式など大学の公式行事では講堂が使用され、多くの神大生がここから巣立っていった」とあります。
この歴史ある講堂も建築後70年以上経過し、現状のまま放置すれば、近い将来使用そのものに支障をきたすことになることは明らかであります。本来、これら修復資金は耐震化工事費を中心に国がその一部を負担すべきものと考えますが、現下の財政事情や大学法人化後の自主運営を基本とする政策の下では、それは期待し難く、資金の大半は同窓会諸兄姉や協賛企業の寄付に頼らざるを得ないのが実情であります。
昨年秋のホームカミングデイの式典で、野上学長自ら「来年の式典は新装なったこの講堂で開催したい」との力強い決意を披露されています。我々同窓会もこの学長の意気に呼応して、伝統的風格と新しい機能を兼ね備えた「多機能型国際文化ホール」としての再生を支援すべく、修復基金の更なる積み上げに協力し、併せて、今秋の式典では工事の完成を祝うと同時に、母校愛から多くの作品を残していただいた中山画伯の遺徳を偲びたいと思っています。
この構想に係わる収支見通しの現状は、同封の「お願い書」に譲ることと致しますが、この由緒ある講堂を母校の象徴的建造物として、現役の学生諸君をはじめ後世に引き継いでいくことが、我々同窓生の役目の一つであると思っています。講堂の再生が、凌霜人の結束を一層高め、併せて、国内外からの優秀な学生・研究者の誘致を通じて六甲台関係部局の活性化の一助になると固く信ずる故であります。新装成った六甲台講堂が、松の緑を背景に存在感を示す光景は、必ずや神戸大学の名所となることは想像に難くありません。加えて、既に多くの卒業生の皆さんからご賛同いただきご厚志を頂戴しているこの事業を、中途半端な形で終わらすことは、何としても避けなければならないとの思いも強くしております。
諸々の計画・予定があるなかで、今回、野上学長・新野六甲台後援会理事長と連名で、講堂修復に的を絞った「お願い書」を同封させていただいておりますのも、以上のような考えからであります。昨年の夏には、何十年かに一度と言われる「竜舌蘭の花」が六甲台に咲き、母校の新しい装いを暗示するようでありました。同窓会諸兄姉のご賛同・ご協力を切にお願いし、この稿を終わります。
次回は、就任時にお約束した「公益法人改革への対応」と「収支改善策」に係わる検
討委員会の状況をお知らせしたいと考えています。
◆第3回ホームカミングデイと神戸大学の未来
法学研究科教授 齊 藤 彰
第3回の神戸大学ホームカミングデイが、9月27日に開催され、当日は全国から多くの卒業生や地域の人々が集い、秋晴れの中で賑やかに交流を深めることができた。
少しだけ個人的な話をすることをお許しいただきたい。海外の大学では、卒業生が年に一度、母校に集まり旧友との交流を温めるという行事が以前から行われてきた。かつて1年間修士課程学生として留学したアバディーン大学(スコットランド)からは、今でも年に2回ほど立派なカラー印刷の冊子が届く。それと一緒に寄付金の呼びかけや大学グッズのカタログも送られてくる。冊子には大学ランキングで母校が何位に入ったとか、連合王国内の大学評価手続で法学部は最高の評価を受けたとかいったニュースが必ず掲載されている。また、これは5年以上も前であるが、たまたまクアラルンプールを訪れた時に、本学経営学研究科の卒業生であるマレーシア人の友人から、神戸大学はどうして海外にいる卒業生のための同窓会を活性化させようとしないのかと質問された。彼の奥さんは日本人で東京の私学の出身であり、その大学はクアラルンプールでも同窓会を定期的に催している。神戸大学には、彼のような立派な卒業生が少なくないにもかかわらず、こうした活動がなく、いつまでも神戸大学の知名度が低いと嘆いていた。
だから神戸大学がホームカミングデイという行事を開始したことや、その切っ掛けとして留学生センターが大きな役割を果たしたことはごく自然に思えた。卒業生との強い絆を構築することは、世界中の大学にとって死活問題となった。しかし、ホームカミングデイの六甲台企画の責任者を私が務めることになるとは思いもよらなかった。今年はたまたま法学部が当番部局となったので、これも何かの巡り合わせであろう。
まず、当日の行事の内容について簡単に紹介したい。午前には六甲台講堂において、全学の企画による式典が行われ、それに引き続いて六甲台本館の前庭で全学主催のティーパーティーが開催された。今年のゲストスピーカーは元浦和レッズでプロとして活躍され、日本代表候補ともなった西野努氏(平5営)であった。
午後からは、六甲台独自の企画として、六甲台講堂では「西野努氏と語る会―浦和レッズと大学経営」とマンドリンクラブ(楽楽・神戸)の総勢約50名の奏者によるコンサートが行われた。懐かしい歌謡曲なども取り入れて工夫されたプログラムで、多くの参加者が楽しんだ。演奏者の皆さんにはまだ暑い時期から、冷房のない六甲台講堂でリハーサルまでしていただいた。これら行事と並行して、学生の企画によって、小川進教授によるマーケティング論の公開講座やキャンパスツアーが開催され、キッズルーム・露店なども多数設営されて、六甲台キャンパス全体を使って卒業生とそのご家族、地域の住民の方々が皆それぞれに秋の一日を楽しんでいただけたことと思う。そして本館前で行われた凌霜会主催による六甲台全体の懇親会では、たくさんの卒業生や現役生が集まり、楽しい交流の場となった。(当日の会場の様子の写真などは神戸大学のHP[http://www.kobe-ac.jp/hcd/index.htm]をご覧いただきたい。)
特に「西野努氏と語る会」では、これからの神戸大学について真剣な議論がなされた。平成5年の卒業生である西野氏に加えて、昭和34年卒業の絹巻康史氏、平成19年卒業の廣岡大亮氏と高田亮氏、そして現役の畝村知里さんにパネリストして登壇していただいた。浦和レッズと西野氏との深い絆がどのようにして築かれたのかを参考にしながら、卒業生・現役生・地域住民そして教職員によって愛され支持される神戸大学になるにはどうするべきかが熱心に議論された。世代が変わっても卒業生が共有するものが確認され、他方で失われつつある良き伝統への危機感も感じた。とりわけ絹巻氏が回顧された、教員と学生とが真の家族のように交わり、社会科学全体を広く深く学ぶことのできる学問的伝統は、これからも神戸大学を支える基盤として、何よりも大切にすべきものであることが明らかとなったように思う。また、母校を愛する優れた卒業生を多数有しながら、そうした方々の力を十分に活用してこなかった責任も強く感じた。西野氏にはご多忙にもかかわらず全日を神戸大学のために割いていただいた。また、この1時間のディスカッションのためだけに東京からお越しいただいた絹巻氏や、企画段階から何日も休日を犠牲にしてくれた廣岡氏、高田氏のような母校思いの卒業生を有していることは、私たちの誇りである。
少しだけ裏方としての話をさせていただきたい。この企画自体の検討は4月から、全学と六甲台とで並行して進められてきた。昨年度は悪天候のせいもあって十分な参加者数を得ることができなかったので、今年はできる限り多くの人たちに集まっていただくことを、まず目標とした。そのためには神戸大学に関心を持つ様々な人々が楽しく集まり、同世代の卒業生だけでなく、現役学生や年齢の違う同窓生とも自由に交流できるようにしたいと考えた。最もよい方法は、この日に神戸大学の卒業生が様々な同窓会を企画してもらうことである。例えば、ゼミ・クラブ・サークル、そしてCOEの研究員などの同窓会も考えられる。今年この試みはまだ十分に成功しなかったが、いくつかの同窓会が9月27日に開催された。ホームカミングデイが夕方5時に終了するので、その夜に各同窓会を三宮などで開催してもらうことができれば理想的である。ホームカミングデイは、家族連れでも楽しめる行事となっているので、同窓会の機会に、家族連れで神戸に来ていただき、母校を見てもらうこともできればとても良いと思う。
こうした企画がなぜ国立大学において十分に展開されてこなかったのかについては様々な理由がある。その根本は、各ステークホルダー間のコミュニケーションが必ずしも十分ではなかったからであろう。この点については、凌霜会の本部事務局が六甲台キャンパスに移ってきた意義は極めて大きい。この積極的な効果として、就職支援も含めて、凌霜会による現役学生のサポートは飛躍的に向上した。六甲台の伝統的な学生組織である3学部ゼミ幹事会が協力して六甲台学生評議会を立ち上げ、春には新入生歓迎会、夏には七夕祭り、卒業時には謝恩会など、学生生活に彩りを添える様々な素晴らしい行事を、凌霜会や六甲台各学部と協力しながら活発に展開するようになった。「しらけ」世代の私から見れば、実に頼もしい後輩たちの姿である。今回のホームカミングデイがもし成功であるとするならば、その大半は凌霜会と現役学生たちが育んだ、六甲台のこの新しい文化に負うものである。
今回の経験から特に感じたことは、卒業生や現役学生だけでなく、事務職員の中に神戸大学を愛する人たちがたくさんおられ、こうした行事に前向きに取り組んでいることである。本館の前庭に学生たちが露店を設営するに当たり、テントをどう配置すれば人々の動線と調和するか、六甲台講堂のドアなどをどう使いこなせば行事が円滑に展開するかなど、事務室に蓄積された沢山のノウハウがある。また、ホームカミングデイ直前には、気持ちよく卒業生を迎え入れるために、事務室の方々が本館後ろの中庭の池の掃除までして下さった。独立法人となった以上、私たちはもっと神戸大学の施設に愛着を持ち、大切に活用して行かなければならない。そうした自覚のためにも、ホームカミングデイは貴重な機会である。
しかし反省点や今後の課題も決して少なくない。それは、特に卒業生の方々の中で、若い世代の出席者が極めて少ない点である。30代や40代だけでなく、50代の卒業生の出席も極めて少ない。こうした世代は働き盛りであり、時間を割きにくいことは明らかだ。しかし、若手・中堅の卒業生に来てもらわないと、本当のホームカミングデイにはならない。忙しい中、1日を使って母校に戻るだけの魅力のあるものに、私たちはホームカミングデイを育てていく必要がある。そのためには現役学生の時から、神戸大学で過ごす時間を人生の中の単なる通過点ではなくて、自分が拠って立つアイデンティティの一部となることを自覚してもらう必要がある。遠くにあっても1年に1日は里帰りしたくなる故郷のような存在にならなければならない。これが理想のホームカミングデイの姿である。しかし、それにはまだまだ時間と努力とが必要である。
卒業生の力なくして、神戸大学に未来はないと真剣に思う。次回のホームカミングデイ(2009年10月31日)には、ぜひ皆さんに六甲台にお越しいただけるよう心よりお願いする次第である。
当日の参加者総数は、大学事務局によると全学で1754名で、法・経・営・国際協力での本部企画参加予定者リストと六甲台企画受付記帳者リストによる卒業(修了)生は137名であった。